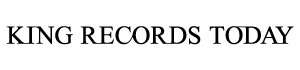麻倉未稀 スペシャル・ロング・インタビュー<Vol.1>~生い立ちからデビュー・アルバム『SEXY ELEGANCE』について~

1981年にデビューし、40年以上のキャリアを持つシンガー、麻倉未稀。彼女がこれまでに残したおよそ200曲の楽曲が、ついに配信解禁となる。「ホワット・ア・フィーリング~フラッシュダンス」に代表される洋楽カヴァーだけでなく、筒美京平の書き下ろし楽曲や昨今ではシティポップの文脈で再評価されるリゾートポップまでバラエティに富んだレパートリーにあらためて驚かされるだろう。
では、麻倉未稀はどのような音楽変遷を経て、数々のヒット・ナンバーを生み出すに至ったのか、そして現在までどのように音楽と向き合ってきたのか、音楽と旅のライター栗本斉を招き、生い立ちからじっくりと語ってもらったインタビューを4回に渡ってお届けする。
~麻倉未稀の生い立ちからデビュー・アルバム『SEXY ELEGANCE』について~
—今回、デビューからのたくさんの音源がついに配信解禁となりました。
麻倉未稀(以下、麻倉):はい、すごく大量にあったみたいですね……。相当あるなとは思っていたんですけど(笑)。
—この機会にテレビに出ている麻倉さんやヒット曲は知っているけれど、過去のご活動を知らない方もいると思うので、詳しくお話を聞かせてください。ご出身は大阪なんですね。どんなお子さんだったんですか。
麻倉:3歳くらいまでは人見知りをしないというか、どこにでもトコトコ行ってしまう子でした。父が登山好きだったので、しょっちゅう私たちはハイキングや登山をさせられていたんです。山に登ると、前から来る人に、「こんにちは、こんにちは」っていうのが楽しくて仕方がなかったことを覚えています。あと、姉が言っていたんですが、いろんなところに行ってしまうのでロープで繋がれていたらしいです(笑)。
—よほどあちこち行っちゃうんですね(笑)。
麻倉:はい、そのくらいお転婆でしたね。
—小さい頃に楽器を習っていましたか。
麻倉:うちにオルガンがあったのでオルガンは習っていたんですけど、小学校に入ってから突然アップライトピアノが運ばれてきて、急にピアノを習い始めさせられたんです。
—ご自身でやりたかったわけではなく。
麻倉:そうです。どうやら母が戦時中でできなかったっていう想いがあったらしく。母のお家はヴァイオリンやピアノを習っていたみたいなんですね。それで、子どもたちにもやらせたいっていうので、オルガンから入ったような記憶があるんですが、途中からピアノに変わりました。私はあまり練習するのが好きじゃなかったので、しょっちゅうピアノの先生に怒られていました(笑)。
—お姉さんも一緒だったんですか。
麻倉:はい、姉はもう真面目にちゃんと習っていましたね。私はピアノの発表会になると急に張り切るっていう(笑)。
—じゃあ、お家でもずっと音楽が流れているような環境だったんですね。
麻倉:そうですね。両親が音楽をやっていたわけではないんですけれど、ステレオがあって、映画音楽などがかかっていましたね。オズモンド・ブラザーズなんかが出演するテレビ番組を日本でも放映していた時代だったので、そういう番組もよく観ていました。父は普段野球中継を観ているんですが、その時間になるとちゃんとそのチャンネルを変えてくれたっていう記憶がありますね。
—最初の音楽体験はどのあたりになるんでしょうか。
麻倉:最初は子供の頃のフォノシートみたいなので、童謡だったりするんですけれど、初めて自分でシングル盤を買ったのが、トワ・エ・モワの「虹と雪のバラード」だったと思います。
—1972年の札幌オリンピックのテーマ曲。ということは小学校高学年くらいですね。
麻倉:その頃、私はNHKの「ステージ101」が大好きだったので、「ステージ101」のアルバムを買ったことも覚えています。姉の影響も結構あるんですよね。だから、クイーンなどの洋楽は、姉が聴いていたものを私も聴いていました。姉が行けないから「行ってらっしゃい」と言われて大阪の厚生年金会館に初めての洋楽のアーティストのコンサートに行ったのがレイ・チャールズでした。
—いい体験ですね。
麻倉:さっぱり知らなかったんですが、行ってみたらすごい人だったっていう(笑)。
—でも、お姉さんも渋い趣味をしていますね。
麻倉:たしかに渋かったですね。スティーヴィー・ワンダーなどを聴き始めたのも、姉からの影響が大きかったですね。ただ中学生ぐらいになると、みんなが通るビートルズみたいなものも聴くようになるんです。
—当時熱心に聴いていた音楽は、他にどういうものがありますか?
麻倉:実はチューリップのファンだったんです。だから最初のアルバム『SEXY ELEGANCE』の時に、上田雅利さんに手伝っていただいた時には言い出しづらくて……。いつ言おうかな、いつ言おうかなと思っていて、結構最後のほうに、「実はチューリップのファンだったんです」みたいな。
—へええ、そうなんですね。
麻倉:中学校の時かな、友達で同じようにチューリップのファンの子がいて、彼女と2人で両親の了解を得て、厚生年金会館にコンサートを観に行ったのを覚えています。確か甲斐バンドが前座で出ていらしたと思います。
—それは貴重ですね。実際に歌ったりバンドをやったりはしなかったのですか。
麻倉:それは全然。ただ、中学生になって歌を習い始めました。というのも、当時「スター誕生」とかオーディション番組が全盛で、歌が大好きなお友達がいてオーディションを受けに行くのに一緒について行って、帰りにあんみつを食べて帰るっていう。あんみつに惹かれて行くみたいな(笑)。
—それは惹かれますね(笑)。その友達の影響はありましたか。
麻倉:いや、まったく自分で歌おうっていう気にならなかったんです。でも、ある時彼女が「一人で受けるのが嫌だから一緒に受けてよ」って言われて。それが、渡辺プロダクションがやっていたスクールメイツのオーディションだったんです。
—あ、テレビではなかったんですね。
麻倉:テレビは絶対嫌だと思っていましたから。その時に何の曲を歌ったか記憶はないんですけれど、受かってしまって。でも母からは「絶対ダメです」って言われました。そこから、歌うことが「ちょっと面白いかも」っていう、スイッチが入ったんですよ。それで、こっそり歌謡学院のオーディションがあったので、受けに行ったんです。そしたら、受かっちゃったんで、母に報告するとまた「断りに行きます」って言われて。
—厳しいですね。
麻倉:それで一緒にお断りしに行ったんですけれど、「オーディションに受かった方は月謝が1ヶ月無料」っていわれて、「落ちた方もいらっしゃるんですよ」って母に説明してくださって。それじゃ申し訳ないからって、「じゃあ1ヶ月通わせます」って言ってくれたんです。それで通っているうちにめちゃくちゃ面白いなと思って。その時中学2年くらいだったんですが、精神的なバランスがあんまりうまく取れない時期だったので、少し登校拒否気味で。でも歌謡学院はしっかり行くので、母もあきれていました。
—居場所を見つけたわけですね。
麻倉:それで、「そんなに好きなんだったら、もうずっと通っていいわよ」って言われて。「通ってもいいけど、ちゃんと学校も行ってください」と言われて。そりゃそうだなと思ったので、先生と色々話して。そこからはずっとお友達とも仲良くしながら学校にも行くようになりました。
—いい話ですね。歌謡学校にはずっと通っていたんですか。
麻倉:中学までです。実はちょうど受験期と重なった頃に、デビューのお話が来たんですね。一瞬迷ったんですけれど、「やってみたい」って言ってレコーディングまでしたんです。でも、声が途中で変わってしまったんですよ。
—変声期に入った?
麻倉:私はがらりと声が変わってしまって。精神的にもあまりアイドルに向いていなかったので、ちょうどいいのかもしれないなあと思ったんです。ただもうその頃には東京の高校を受けちゃっていたっていう。
—それは確信犯的な?
麻倉:確信犯です(笑)。先生との面談で、「私東京行きます!」みたいなそんなノリで言っていて。先生がびっくりして母に電話したら、母も「えっ?」って思ったらしいのですが、「まあ、本人がそういう風に言うんであれば」ということで、先生も東京の学校を調べてくださって。今考えるとすごくわがままだったなと思いますね(笑)。

—オーディションもそうですけれど、麻倉さんはなかなかの策士ですね(笑)。
麻倉:ただ、住む場所が家の事情で決まっていて、そこに近い学校を探しなさいって言われたので、あまり選択肢がなかったんです。でも、そこに受かっちゃったんで、母も「仕方がないわね」って言って。父は父で諦めてっていう。だからといってデビューが決まったわけでもなく、ただ東京に行ってちゃんと勉強したいからっていう理由で。—高校生活はどうでしたか。
麻倉:それがもう、高校3年間めちゃくちゃ面白くてですね(笑)。友達がみんな、面白くて。
—部活とかではなく。
麻倉:部活は途中までダンス部だったんですけれど、部活をしていると歌のレッスンが行けなかったので、途中でやめてしまって。ちょっと残念だったんですけど。ただなぜか「放送部を手伝って」って言われて、放送部には出入りしていました。先生方も気さくに色んなことをちゃんとさせてくれて。
—良い学校だったんですね。
麻倉:良い学校でしたね。あまりの楽しさにあんまりレッスン行ってなかったくらい(笑)。住まいはマンションの一室を貸りていたので、みんなが私の部屋に来てくれました。「卒業がまずそう」っていうと、家に来て泊まり込みで勉強教えてくれたこともあったし、とにかく楽しい3年間を過ごしました。
—じゃあ、高校時代は学生生活をエンジョイしていたわけですね。
麻倉:そうですね。その間にレコード会社のオーディションを受けたり、コマーシャルソングを勉強のためにお手伝いさせて頂いたりもしました。
—高校を卒業された後は?
麻倉:卒業してからは、少しだけアルバイトしたいなって思ったんです。高校時代、母からは「アルバイトは絶対禁止!」って言われていたんですね。卒業してからは、本当は大学に行きたかったんですけど、高校3年間はなんだかんだ言って親が投資してくれていたということもあったので、さすがに大学までって言えないなと思って。ちょっとアルバイトしたいなって言ったら、 姉が母を説得してくれて。その間に雑誌「装苑」のモデルオーディションを受けたんです。
—それはまた違う展開になりましたね。
麻倉:実は姉が「ミセス」の専属モデルをやっていたんですね。もう全然身長が私と違うんです。それで、時々「姉妹でモデルを」って声をかけてもらって、私が姉のページを手伝うことがあって。そうしたら編集長の方が「モデルを募集しているから、妹さんにオーディション受けるように言ってみて」っていう風におっしゃってくださって。私はファッションモデルっていうと、身長が高くないといけないっていうイメージがあったんですが、「いろんなページがあるので」って言われて、「あ、なるほどな」と。姉からも「これからあなたがもしデビューをするのであれば、ちゃんとファッションも勉強しておいた方がいいわよ」って言われて、これも納得して。それでオーディションを受けたら受かって、「装苑」のモデルとして1年間くらいやったのかな。その間にデビューが決まったんです。
—じゃあモデルやったことがプラスになったんですね。
麻倉:なりましたね。逆に言えば、デビュー曲の「ミスティ・トワイライト」は、オンワード樫山の「ジェーン・モア」っていう婦人服ブランドのコマーシャルソングだったっていうこともあったので、そういう部分では「装苑」のモデルだった私が歌うっていうことが言えるのはよかったのかなっていう風には思いますね。
—そのデビューのきっかけは、どういう流れだったのでしょうか。
麻倉:もともと「ミスティ・トワイライト」は英語詞があって、すでに「ジェーン・モア」のコマーシャルソングとして流れていたんですね。オンワードさんには視聴者の方から、「あれはレコードで買えるのか」っていう問い合わせが非常に多かったらしいんです。それで、制作会社の方にこの曲をレコード化しないかっていうお話があったんです。元々の英語の部分はサンディー・アイさんが歌っていらして。それで、レコード化するのにオーディションをやろうっていうので、私もそこでオーディションを受けて。ただレコード会社をどこにするかは決まっていなくて、何社か打診したらキングレコードさんがすぐに手を挙げてくださったという流れなんです。
—まず曲があって、歌い手を決めて、レコード会社が決まったと。普通とは流れが逆ですね。
麻倉:コマーシャルソングでは、そういうパターンが多いみたいです。だから「ミスティ・トワイライト」は、前後のメロディを付け足しているんです。作詞の竜真知子さんと作曲の大野雄二さんが前後を付け加えてひとつの曲に仕上げてくださったそうなんです。
——そうなんですね。ということは、CMタイアップありきで、歌手・麻倉未稀は生まれたということですね。
麻倉:そうですね。
—少し調べてみたら、「ミスティ・トワイライト」は1981年8月に発売されて、シングルチャートで31位を記録しています。それなりにヒットしたってことだと思うのですが、その感覚はありましたか。
麻倉:まったくなかったですね。でも、結構いろんなラジオ番組などでかけてくださってたようです。たしか北海道で結構売れたんですよ。だから月に2、3回は北海道に行って番組に出していただいていましたし、そういうのは非常に嬉しかったですね。その当時は、アイドル全盛の頃だったんです。でも私のレコードを買いに行く方が、サラリーマンの方が多かったから「サクラが買っているんじゃないか」って言われたこともあったようです。あと、カーオーディオでの需要があったみたいで、彼がドライブに連れて行ってくれて、かけた曲が私の曲で、「それで聴いてファンになったんです」っていう女性が結構多かったです。
—へええ、そうなんですね。
麻倉:だからサラリーマンの方には非常に感謝しています(笑)。
—サラリーマンの方をターゲットに作っていたわけでもないんでしょうけれど、きっと麻倉さんはデビュー当時から大人っぽいイメージがあったので、アイドルでは物足りない大人の男性に支持されたんでしょうね。
麻倉:精神的には子どもだったんですけどね。だから「しゃべるな」ってよく言われたんです。「口チャック!」みたいな(笑)。
—「ミスティ・トワイライト」のジャケット写真もすでに貫禄ありますもんね。

麻倉:そうなんですよ、だから、アイドルの人たちからは「ちょっと怖くてしゃべれない」とか言われてたみたい。随分経ってから、太川陽介さんと旅の番組でご一緒した時に聞いたんですけれど、当時NHKで太川さんが司会していらっしゃる番組があったじゃないですか。その番組に出た時に、「なんだ、こいつ、しゃべらないヤツだな」と思っていたって。「えっ?こんなにしゃべる人だったっけ?」って言うから、「ごめんね、あの時あんまりしゃべるなって言われていてね、口チャックしていたの」って(笑)。
—なるほど(笑)。
麻倉:「大人っぽい曲だったもんね。しゃべるとバレちゃうよね」って(笑)。
——話を戻すと、「ミスティ・トワイライト」が初のレコーディングですよね。その時のことって覚えていますか。
麻倉:よく覚えています。大野雄二先生もいらしていて。歌のダビングの時もずっとつきっきりでレコーディングしてくださいました。私が緊張しようものなら肩揉んでもらったり、差し入れもしてくださって「これ食べなさい、あれ食べなさい」って言ってくださったり(笑)。
——大野さんはトークも面白いですもんね。
麻倉:そうそう、駄洒落ばっかり。最初はなんだか怖いなって思っていたので、見た目と雰囲気が全然違う方で面白いなと思いました。「ふわふわって歌ってくれればいいんだよ」って。「もっと肩の力抜いて」って言って、ずっとつきっきりでした。
——じゃあ、レコーディングして、シングルもリリースして、キャンペーンも行って。その後すぐにアルバムを出すことは決まっていたんですか?
麻倉:もう出すことは決まっていました。そのアルバムを「どういうのがいいのか」って言われても私…、みたいな感じだったんですけれど。
——麻倉未稀をこう売り出すというようなコンセプトはあったんですか?
麻倉:あの、今では絶対使わないキャッチフレーズなんですけど「都会の美人シンガー」っていう(笑)。
—その通りじゃないですか(笑)。
麻倉:都会的で大人っぽいアルバムを作ろうっていうのは言われていて。さっき話に出たチューリップの上田さんが始めたバンドのメンバーにも参加してもらって、そのピアノの鈴木宏二さんがアレンジもできるというので半分くらいの曲を編曲してもらいました。
—それがファースト・アルバムの『SEXY ELEGANCE』ですね。他にも瀬尾一三さん、若草恵さん、大谷和夫さんなどもアレンジを手掛けていらっしゃいますが、バラエティに富んでいて、全体的にはやはり大人っぽい印象です。

麻倉:やはり狙っているところはそのイメージでしたね。「ひきしお」とか「今夜だけ恋人」などはけっこう良い曲で、高校生ぐらいの時からこういった感じの大人の歌を歌いたかったっていうのもありました。ただ実際に自分の精神と合っているかというと、まだちょっとついていけてなかったところも沢山ありますね。今歌えばもうちょっとちゃんと歌えるのに、みたいな(笑)。
—この当時はアイドル全盛時代でありましたが、その一方で阿川泰子さんのような美人ジャズシンガー・ブームみたいなのもありましたし、門あさ美さんや水越けいこさんみたいな大人っぽいシンガー・ソングライターも売り出していました。
麻倉:多分そういう路線を狙っていたのだと思います。デビューが一緒なのは、堀江淳くんや泰葉ちゃんなど。いわゆる今で言うシティポップって言われているような音楽をやろうとしていたんでしょうね。
過去の作品から最新作まで全200曲に及ぶ楽曲配信をスタート!

各配信サイトはこちら
https://bio.to/MikiAsakura_200
特設サイトはこちら
https://cnt.kingrecords.co.jp/miki_asakura200/
麻倉未稀プロフィール
1981年、CMソング「ミスティ・トワイライト」でデビュー。伝説のTVドラマ「スクール・ウォーズ」「スチュワーデス物語」 の主題歌「HERO」「What a feeling~FLASH DANCE」はいまだに強烈な印象を残す。
ジャンルを超えたその類まれな歌唱力は折り紙つきで、実力派歌手が苦手とする、カラオケマシーンによる採点で勝負を決める「カラオケ★バトル芸能界NO1決定戦」(TV東京)で見事優勝し、カラオケマシーンさえも太鼓判を押す歌唱力!と喝采を浴びる。現在は、歌の活動のみならず、ミュージカル等の舞台や、旅番組のレポーターとしても活躍。2017年にTBSテレビ「名医のTHE太鼓判!」にて乳がんが発覚。全摘手術を受けるも奇跡的な回復にて、術後3週間でステージに復帰。その後も精力的に音楽活動を続ける。更に2018年には地元の藤沢にて「ピンクリボンふじさわ」を立ち上げる。その他「ピンクリボンウォーク」、「ピンクリボンシンポジウム」など乳がん検診の啓発運動にも積極的に参加し続けている。
栗本斉プロフィール
音楽と旅のライター、選曲家。1970年生まれ、大阪出身。レコード会社勤務時代より音楽ライターとして執筆活動を開始。退社後は2年間中南米を放浪し、帰国後はフリーランスで雑誌やウェブでの執筆、ラジオや機内放送の構成選曲などを行う。開業直後のビルボードライブで約5年間ブッキングマネージャーを務めた後、再びフリーランスで活動。著書に『ブエノスアイレス 雑貨と文化の旅手帖』(毎日コミュニケーションズ)、『アルゼンチン音楽手帖』(DU BOOKS)、共著に『喫茶ロック』(ソニー・マガジンズ)、『Light Mellow 和モノ Special』(ラトルズ)などがある。2022年2月に上梓した『「シティポップの基本」がこの100枚でわかる!』(星海社新書)が話題を呼び、各種メディアにも出演している。